桔梗信玄餅の歴史


観光土産品の不在と洋菓子の進出
桔梗信玄餅の開発以前、山梨の土産と言えば、生ぶどうを砂糖の衣で包んだ「月の雫」というお菓子と、果実のぶどうや桃といったもの以外に目立ったものはありませんでした。
しかし、生の果実やそれを使ったお菓子は一年を通じて販売することができず、非常に不便な状態だったのです。
また、昭和35年頃から洋菓子ブームとなり、県外の洋菓子専門店が進出し始め、これに対抗すべく当社三代目であった故・中丸幸三を中心に新製品の開発に懸命に取り組みました。
日本人の嗜好に合うものは何かを出発点にして開発に取り掛かり、そこから生まれたのが「桔梗信玄餅」でした。

「安倍川餅」が発想のヒント
桔梗信玄餅の開発のヒントに「安倍川餅(あべかわもち)」があります。
山梨県には古来よりお盆の時期に、餅にきな粉と黒蜜をかけた安倍川餅を供えて食べる習慣があります。これをヒントに現代風に小さくまとめ、お盆だけでなく一年中食べられるものにしたのが、「桔梗信玄餅」です。
今では各地に類似したものがありますが、当時、風呂敷で包むという形態はまったくない斬新なものでした。
「お客様に包装を解いてもらい、別容器の黒蜜をかけてもらうというのはいかがなものか、売れるわけがない」と同業者から冷ややかな声もありましたが、昭和43年の正月、最初の試作品ができ、その夏販売に踏み切りました。
発売後はユニークな包装も話題となり、お客様からの反応は好評でした。添加物などを一切使用しないお餅のなんとも言えない素朴な味わい、黒蜜の独特な舌触りは、「桔梗信玄餅」ならでは。
姿かたちをまねただけでは作り出せない、桔梗屋ならではのものです。

空前の信玄公ブーム
更に幸運なことに、タイミングよく発売した翌年から武田信玄と上杉謙信の戦いを描いたNHK大河ドラマ「天と地」(原作:海音寺潮五郎)が放送開始。さらに「風林火山」(原作:井上靖)も映画化され、空前の武田信玄ブームとなりました。
日本中から山梨県に観光客が訪れました。それまで富士山といえば静岡県を思い浮かべる人が多かったのですが、それ以降、山梨県にも、富士山あり清里あり富士五湖あり、優れた観光県だとの認識が高まりました。その年の一年間、山梨県は商業ベースに乗って大変な観光ブームになりました。
こうしたマスメディアの力もあり桔梗信玄餅は山梨の銘菓として定着していきました。その後も売り上げは大幅に伸び続け、発売時日産5000個だったものが6年後には日産5万個、今では日産12万個に達しています。
桔梗信玄餅の製造工程

衛生管理
作業に入る前、製造に携わる者は全員清潔な白衣・帽子・マスク・靴に着替え、必ずエアシャワーに入ります。
エアシャワー通過後は、粘着ローラーで再度細かな埃を取り、両手を3秒間アルコール消毒することで初めて製造部の通路に入ることができます。
さらに、通路から各部屋に入る前にも再度アルコール消毒をしなければなりません。この徹底した衛生管理の下、桔梗信玄餅は作られています。

蜜詰め
桔梗信玄餅といえば、きな粉とお餅、そしてトロッとした濃厚な黒蜜。他の類似商品やスーパーなどで販売されている黒蜜と比べれば、独特の濃厚さがおわかりになるでしょう。
黒蜜が入ったタレビンは、今でこそ全自動(もちろん桔梗屋特注の蜜詰機です)ですが、昔は手作業で一瓶ずつスポイトで入れ、フタを閉めていました。
蜜を詰めた後はベルトコンベアに乗せられ、熱湯の中へ。85℃以上で5分間、しっかりと殺菌されます。
1枚の番重(クリーム色のトレー)に550本のタレビンが入っています。時期により差はありますが、1日に製造する量は番重200~250枚にもなります。

餅煉り
桔梗信玄餅のお餅は、餅粉、砂糖、水飴だけを使用しています。餅練り機の中では大きな歯がゆっくり回転し、原料を滑らかになるまで混ぜ合わせます。
練りあがったお餅は番重に一枚一枚取り分けられていきます。柔らかいお餅の取り分けは、切る人と番重を持つ人の息を揃えなければ扱えません。
番重に取り分けたお餅はそのまま1~2日間寝かされます。つきたてのお餅は柔らかすぎて機械で上手くカットができないからです。また、寝かせることでおいしいと感じる弾力が生まれます。番重一枚で桔梗信玄餅150個位のお餅が取れます。

包装
包装の部所は、いくつもの大型機械が連結して稼動しています。最初の機械にお餅を入れると、一口大になったお餅が3個ずつ、きな粉にまぶされて出てきて、そのままカップに収まり、次の機械へと自動的に流れていきます。
次の機械から出てくると、カップの下にビニールの風呂敷、カップの上には透明のフタと黒蜜のタレビンが乗っています。そして大勢の職人の手によって1つずつ丁寧に2度結ばれ、再びラインに乗せられて次の機械へと運ばれていきます。
工場見学にいらしたお客様が驚かれるのは、従業員の多さと結ぶ速さ。熟練職人ともなると、2度結びにかかる時間はおよそ6秒。中には手作業で結んでいることを知らず、大変驚かれるお客様も。他の工程では、機械の導入により作業の自動化が進んでいますが、この工程は機械に任せるわけにはいきません。手作業により、ふわっとした手作りの温かさが生まれています。
ラインから集まった桔梗信玄餅は、ベルトコンベアに乗り金属探知機を通過します。ここでは同時に重さも量り、異常があったものは自動的に弾かれます。この機械が異物混入を未然に防ぎ、安全・安心な製品を生産します。
製造の最終工程、袋詰め・箱詰めと包装です。桔梗信玄餅の袋といえば、桔梗の花柄を入れた赤・紺・白の3色。贈る相手の好みや年齢で選ぶのも楽しいですね。
不織布の信玄袋はなかなか丈夫。空になった袋や箱を捨てずに小物入れにしてくださるお客様もいるそうです。
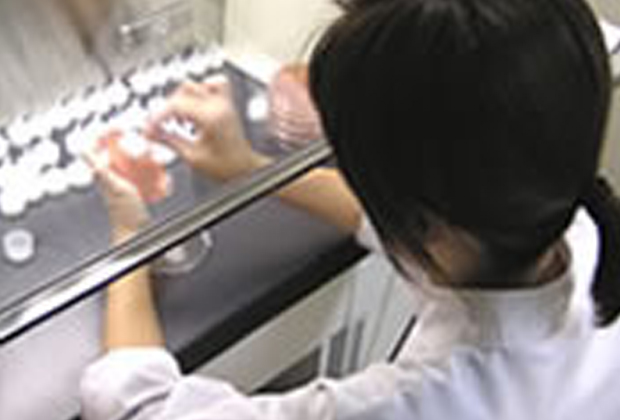
品質検査
品質管理室にて、製品の一般生菌および大腸菌群検査を行います。工場内の拭き取り検査、落下菌検査(空気中の一般生菌および真菌(カビ・酵母)の検査)のほか、日持ち検査や製品の硬度なども検査します。製品の変質・異常はないか、様々な角度から検証し、厳しい品質検査を経て、安全・安心な製品が完成します。

商品センター
仕上がった製品は「商品センター」に集められ、直営店やお土産店、ホテル、キヨスク等に運ばれていきます。商品センターは桔梗信玄餅だけでなく、桔梗屋が扱う全ての商品、包材を管理しています。
桔梗信玄餅10個入の場合、1枚のパレットに640箱が乗っています。そのパレットが商品センターには最大230枚収納でき、オートメーション化されたリフトにより管理されています。年末年始、お盆、ゴールデンウィークなど観光シーズンが近づくにつれ、保管区が桔梗信玄餅でいっぱいになります。 桔梗信玄餅は、衛生管理から製造、検査、そして配送まで、最新の機械設備と多くの人の手によってお客様の元へ届けられています。
桔梗信玄餅の受賞歴
| 第19回 | 山梨県工業展示知事賞 受賞 |
|---|---|
| 第5回 | 山梨県土産品コンクール 第一位 |
| 第5回 | 日本商工会議所会頭賞 受賞 |
| 第19回 | 全国菓子大博覧会名誉総裁賞 受賞 |
| 2012年 | モンドセレクション金賞 受賞 |
| 2013年 | モンドセレクション金賞 受賞 |
| 2014年 | モンドセレクション金賞 受賞 |
| International High Quality Trophy 受賞 | |
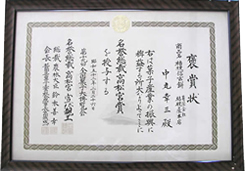
平成15年1月、桔梗信玄餅は山梨土産売り上げNo.1(全国で第15位)であることが報じられました。 また、平成17年には、国土交通省主催の「VJC(Visit Japan Contest)外国人が選ぶ魅力あるお土産コンテスト」で銀賞を受賞しました。
桔梗信玄餅のお召し上がり方
その1
容器にお餅が三切れ入っておりますので、中の一個をようじで持ち上げたところへ黒蜜を入れ、きな粉と混ぜてお召し上がりください。

1.風呂敷を開く
風呂敷を開いて中蓋を取り外します。

2.お餅を持ち上げる
お餅を持ち上げます。

3.黒蜜をかける
お餅を持ち上げたところに黒蜜をかけます。

4.きな粉とよく混ぜて食べる
黒蜜ときな粉をよく混ぜてお召し上がりください。
その2
ようじを使い、きな粉をお餅の下に入れ込むようにして黒蜜をかけてお召し上がりください。

1.風呂敷を開いてきな粉をかきまぜる
風呂敷を開いて中蓋を取り、ようじできな粉をかき混ぜます。

2.きな粉をお餅の下へ
あせらずゆっくり、きな粉をお餅の下にしまい込みましょう。

3.黒蜜をかけて
きな粉がお餅の下へ隠れたら、黒蜜をかけ、きな粉と黒蜜をよくつけて食べましょう。
その3
お餅を風呂敷の上に取り出し、容器の中に出した黒蜜につけてお召し上がりください。

1.風呂敷を開いてお餅を取り出す
風呂敷を開いて中蓋を取り、ようじできな粉をかき混ぜます。

2.黒蜜にディップ
取り出したお餅を黒蜜ときな粉につけて食べます。
容器の中に残った黒蜜ときな粉はよく混ぜて。最後まで美味しく食べられます。
番外編
広げた風呂敷の上にお餅ときな粉をのせ、黒蜜をかけ、風呂敷を包むようにお餅をもんできな粉と黒蜜をよく混ぜお召し上がりください。

1.風呂敷を開く
風呂敷を開いて中蓋を取り、容器の中身を風呂敷の上にすべて出します。

2.黒蜜をかける
お餅の上に黒蜜をかけます。

3.四隅をもって混ぜる
風呂敷の四隅をまとめるようにして持ち上げ、手のひらでお餅をもみ込みます。
黒蜜ときな粉をよくなじませましょう。
番外編2
桔梗信玄餅とお好みのアイスでつくろう!

桔梗信玄餅とお好みのバニラアイスを用意し、お皿に盛り付けてきな粉と黒蜜をかけたらお家で簡単!桔梗信玄餅アイス風。

器や盛りつけ方を変えるだけで雰囲気も変わります。
アイスをつみあげて高さを出したパフェ風やスティックタイプのアイスも食べやすいですよ。

より桔梗信玄餅アイスを感じたい方にはアイスときな粉、黒蜜をよく混ぜ、お餅をつけて食べるディップスタイルをおすすめします。
手早く混ぜてアイスが溶けすぎないうちにお召し上がりください。
